「眠いわけでもないのに、なぜかあくびが止まらない」
このような悩みを抱える方が、近年増えています。
単なる疲れや睡眠不足と思いがちですが、実は体からの重要なサインである可能性もあります。
この記事では、あくびが止まらない原因とその対処法、考えられる病気との関係について、医療情報をもとにわかりやすく解説します。
あくびとは何か?―その役割と仕組み

あくびは、深く息を吸い込みながら口を大きく開ける一連の反応です。
多くは「眠いとき」「退屈なとき」に起きる自然現象ですが、実際は次のような目的を持っています。
- 脳の温度を下げ、覚醒させる
- 酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出する
- 脳や身体を活性化させる信号
つまり、あくびは「眠気」や「疲労」のサインであると同時に、自律神経や脳の状態を調整するための機能とも言えます。
あくびがたくさん出るのはなぜ?
一日に何度もあくびが出ると、「もしかしておかしいのかな?」と不安になりますよね。
その原因として多く見られるのは次の3つです。
- 慢性的な睡眠不足
- 過度な肉体的・精神的疲労
- 低酸素状態(マスク着用・浅い呼吸など)
特に最近では、スマホの使いすぎやマスク生活による酸素不足、呼吸の浅さが影響しているケースもあります。
あくびが止まらないのはストレスのせい?
ストレスもあくびの一因です。
ストレスが蓄積すると、自律神経のバランスが崩れ、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなります。
この結果、体がリラックス状態に移行できず、眠くないのにあくびが頻発する「生あくび」が出るようになるのです。
特に以下のような方は注意が必要です:
- 慢性的に緊張状態にある
- 睡眠の質が悪い
- ストレスをうまく解消できていない
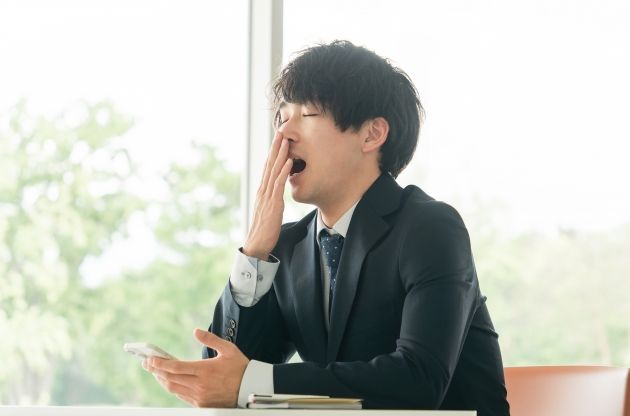
あくびと涙の関係とは?
あくびをすると涙が出る経験はありませんか?
これはあくびによって顔の筋肉や涙腺が刺激されるために起こる自然な反応です。
涙が出やすい人は、以下のような状態にあるかもしれません:
- 眼精疲労やドライアイ
- 自律神経の不安定さ
- 感情の不安定さ
涙の量が異常に多い、または目の症状がある場合は、眼科の受診をおすすめします。
あくびが止まらないのは病気のサイン?
以下のような病気が隠れている可能性も否定できません。
| 疾患名 | 特徴・症状 |
|---|---|
| 睡眠時無呼吸症候群 | 睡眠中に呼吸が止まり、日中の強い眠気とあくびを引き起こす |
| 脳梗塞や脳腫瘍 | 酸素不足により、無意識のうちにあくびが頻発。他にしびれや言語障害を伴う場合も |
| 貧血 | 酸素運搬能力が低下し、脳に酸素が行き届かずあくびが出る |
| 自律神経失調症 | 疲労・不眠・ストレスで自律神経が乱れ、過剰なあくびを誘発 |
※症状が長期にわたって続く場合や、頭痛やめまい・しびれなどを伴う場合は、医療機関を受診してください。
疲れとあくびの関係
疲労がたまっていると、身体は「もっと休んでほしい」というサインを発します。
その一つがあくびです。
- デスクワークで目や脳が疲れている
- 長時間同じ姿勢でいる
- 休息が足りていない
これらは生理的なあくびを誘発しやすくなる要因です。意識的に休憩を取り、体と心のバランスを整えることが必要です。
頭痛とあくびの意外な関係
頭痛の前兆として「あくびが増える」ことがあります。
これは、偏頭痛の初期症状として知られています。
脳の血管が拡張し、脳に酸素を供給しようとする過程で、自然にあくびが出るようになります。
このような場合は、以下の症状に注意してください:
- 脈打つような頭痛
- 目の奥が痛い
- 吐き気や光過敏がある
偏頭痛の疑いがある場合は、神経内科や脳神経外科での診察を検討してください。
あくびが止まらないときの対処法

あくびが出るのは体の自然な反応ですが、すぐにできる対策もあります。
1. 深呼吸をする
鼻からゆっくり吸って、口からゆっくり吐く。これを数回繰り返すと、自律神経が整い、脳への酸素供給が改善されます。
2. ストレッチや軽い運動
肩を回す、首を伸ばすなどの軽い動作でも、血流が良くなり眠気が軽減されます。
3. コップ一杯の水を飲む
水分補給で脳が活性化します。特に朝一番や集中力が切れたタイミングに効果的です。
4. 仮眠をとる(10〜20分)
可能であれば、短時間の仮眠をとることで脳がリフレッシュされ、あくびも減少します。
5. 睡眠の質を見直す
毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のスマホを控えるなど、生活習慣の見直しも重要です。
6.強制的に止める方法
あくびが出そうになる寸前に舌を出すと止まります。そのメカニズムは解かっていませんが確実に止まります。マスクや手で覆ったら隠しやすいです。
医療用語としての「あくび」
医学的には「あくび」は「Yawning(ヤウニング)」と呼ばれ、以下のような状況に関連づけられます。
- 脳幹の活動状態
- 視床下部・自律神経の反応
- セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の関与
また、「生あくび(なまあくび)」という言葉は、眠くないのに出るあくびを指し、疾患の前兆として重要視されます。
まとめ:あくびが止まらないときは体からのSOS
あくびは、ただの眠気のサインではなく、「ストレス」「疲労」「自律神経の乱れ」「病気の前兆」など、さまざまな要因を反映するものです。
- 睡眠・生活リズムを整える
- 深呼吸や運動でリフレッシュ
- 症状が続く場合は医療機関へ
あくびは体からの小さなSOSサイン。
その声に気づき、日々のケアに役立てていきましょう。

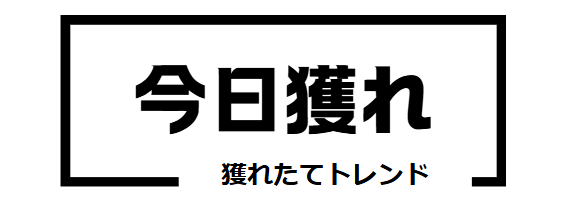
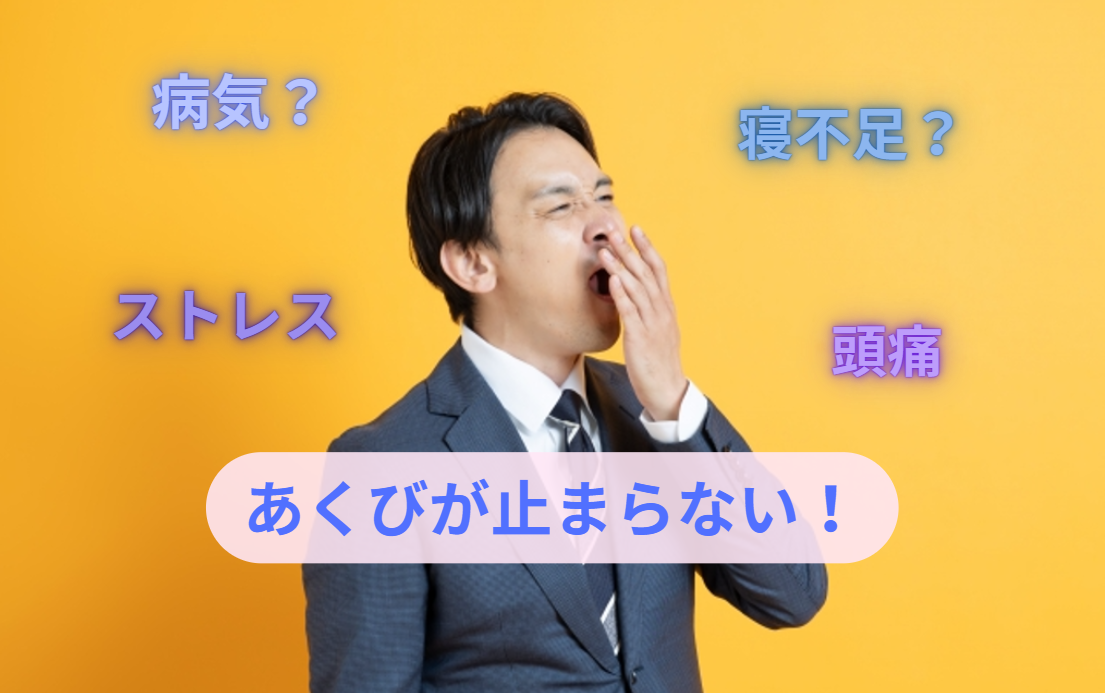
コメント